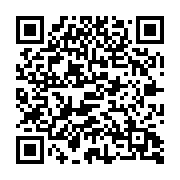医療事務のクレーム対応|基本の流れを押さえよう

医療機関において、受診者からのクレームは避けられないものです。しかし、適切な対応により、むしろ医療サービスの質を向上させる機会として活用することができます。
クレーム対応は、以下の三段階のプロセスを意識することで、より効果的に行うことができます。
傾聴:まずは相手の話に耳を傾ける
クレーム対応の第一歩は、受診者の声に真摯に耳を傾けることから始まります。
受診者が不満を感じる背景には、多くの場合、医療機関に対する期待と実際のサービスとのギャップが存在します。このギャップを理解するためには、まず受診者の立場に立って話を聞く必要があります。
ここで重要なのは、単に黙って聞くだけでなく、適切な相槌や共感の言葉を交えながら積極的に傾聴することです。
受診者の話を遮ることなく、最後まで聞き切ることで、医療機関側の理解しようとする姿勢が伝わり、それだけでも不満が軽減されることがあります。
謝罪:気持ちに寄り添った謝罪を

受診者の話を十分に聞いた後は、適切な謝罪が必要です。ここでのポイントは、具体的な状況に即した謝罪を行うことです。
待ち時間が長かった場合は「お待たせして」、不快な思いをさせた場合は「ご不快な思いをさせてしまい」など、状況に応じた言葉を添えることで、より誠意のある謝罪となります。
ただし、全面的な謝罪は避けるべきです。医療機関側に全ての責任があるわけではない場合、「全ておっしゃる通りです」といった包括的な謝罪は、その後の適切な解決を困難にする可能性があります。
状況を正確に理解した上で、必要な範囲での謝罪を心がけましょう。
提案:納得していただける解決策を提案

最後のステップは、具体的な解決策の提示です。この段階では、受診者のニーズを正確に理解した上で、実現可能な提案を行うことが重要です。
場合によっては、その場での即断を避け、上司や関係部署と相談した上で、より適切な解決策を提示することも必要です。
また、クレームを提起してくださったことへの感謝の意を示すことも重要です。これにより、医療機関の改善に向けた前向きな姿勢を示すことができ、受診者との良好な関係構築にもつながります。
時には、受診者自身が自分の伝え方を振り返り、謝意を示してくださることもあります。
このように、クレーム対応を単なる苦情処理ではなく、医療サービス向上の機会として捉えることで、より建設的な解決が可能となります。
これは個々の医療事務職員のスキルアップだけでなく、医療機関全体のサービス品質向上にも寄与する重要な業務といえるでしょう。
おわりに
医療事務におけるクレーム対応は、傾聴、謝罪、提案という三つの要素が密接に関連し合う継続的なプロセスです。
まず受診者の声に真摯に耳を傾け、その上で適切な謝罪を行い、最後に具体的な解決策を提案するという基本的な流れを意識することで、より効果的な対応が可能となります。
この一連のプロセスを通じて、受診者の信頼を回復し、より良い医療サービスの提供につなげることができるのです。
クレームを恐れるのではなく、むしろ改善の機会として前向きに捉え、日々の業務に活かしていくことが、医療事務職員には求められています。
会員登録がまだの方へ
- 転職エージェントからのスカウトが届く
- 非公開求人にもエントリーできる
- 転職サポートを受けられる
他にもさまざまなメリットが受けられます。まずはお気軽にご登録ください。